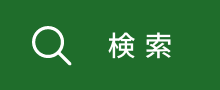
オープンアクセス
岩手大学におけるオープンサイエンスへの取組み
岩手大学では、研究成果のオープンアクセス化を推進するため、凤凰体育平台2年2月26日に「岩手大学オープンアクセス方針」を策定しました。
オープンアクセス(以下、「OA」と記載)とは、研究の成果物である学術論文等がインターネット上で公開され、誰でも無料で利用できる状態にあることをいいます。研究成果の公開することで、以下のような大きな意義を持ちます。
研究者のメリット
- 自身の研究成果をより多くの人に見てもらうことが出来る
- 論文を引用される可能性が高まる
社会全体でのメリット
- 分野を超えた研究成果の共有による、研究の更なる発展やイノベーションの創出が期待される。
- 研究成果が社会に還元されることで、社会の発展に寄与する。
本学では、これまでも岩手大学リポジトリを通じて、本学の研究成果を世界に向けて公開してきましたが、今後より一層のOA化を推進し、学術研究のさらなる発展に寄与するとともに、国際社会の発展に貢献していきます。
OAの方法
OAを実現する方法は、次の2つがあります。
- グリーンOA
大学等が構築?運用する機関リポジトリや分野別リポジトリ?プレプリントサーバ上に、自身で論文を登録することにより、論文をOA化する方法です。
なお、ジャーナルに掲載された論文をリポジトリに登録する場合は、出版社の規定により、多くの場合は査読済み最終稿(著者最終稿)を登録することになります。また、出版社や雑誌によっては、著者稿の公開にあたって一定の公開禁止期間(エンバーゴ)を設けている場合もあります。
本学では 岩手大学リポジトリという機関リポジトリを運用しており、本学に所属する研究者や学生は岩手大学リポジトリを利用することで自身の論文を「グリーンOA」として公開することが可能です。 - ゴールドOA
APC(Article Processing Charge、論文投稿料)を支払う等により、ジャーナルのオープンアクセスオプションを選択し、論文を出版と同時にOAにすることができます。
ただし、ジャーナルの中には、APCの収益を目的とした粗悪な学術誌(いわゆる「ハゲタカジャーナル」)も存在しますので十分にご注意ください。
- 岩手大学での支援策
ゴールドOAの実施にあたり、岩手大学で実施している支援策(OA出版枠の提供、APCの割引等)をまとめています。以下ページよりご確認ください。
学術論文等の即時オープンアクセス義務化
公的資金による助成を受けた学術論文等(2025年度新規公募分より)の即時オープンアクセス(OA)義務化の基本方針が発表されました。具体的に研究者に求められていることは何か、岩手大学ではどのような対応が出来るのか紹介します。
- 研究者に求められていること
公的資金のうち2025年度から新たに公募を行う 即時オープンアクセスの対象となる競争的研究費 を受給する者は、当該研究費による 学術論文及び根拠データ の学術雑誌への掲載後、即時に機関リポジトリ等の情報基盤への掲載を義務づけられます。- 対象となる競争的研究費
?JSPS 科学研究費助成事業
?JST 戦略的創造研究推進事業(一部を除く)
?AMED 戦略的創造研究推進事業
?JST 創発的研究支援事業
- 対象となる学術論文及び根拠データ
?学術論文:電子ジャーナルに掲載された査読済みの研究論文(著者最終稿を含む)
?根拠データ:掲載電子ジャーナルの執筆要領、出版規程等において、透明性や再現性確保の観点から必要とされ、公表が求められる研究データ
- 対象となる競争的研究費
- 岩手大学での対応
本学では 岩手大学リポジトリという機関リポジトリを運用しており、本学に所属する研究者や学生は岩手大学リポジトリを利用することで自身の論文を「グリーンOA」として公開することが可能です。
また、公開する研究データは、GakuNinRDMを利用し、公開することが可能です。 - 公的資金により生まれた学術論文等の即時オープンアクセスに関する学内説明会(学内限定)
オープンアクセスに関する取り組みを進めるにあたり、開催した説明会の動画及び資料を以下のページに掲載しております。 - 参考資料
岩手大学研究データ管理?公開ポリシー
- 岩手大学研究データ管理?公開ポリシー
岩手大学は2024年4月25日に「岩手大学研究データ管理?公開ポリシー」を策定しました
これは、岩手大学の研究者が研究活動によって得られた研究データの適切な管理?公開および利活用を促進するとともに、研究の健全性と公正性を確保し、さらなる学問研究の発展と社会への還元を進めることを目的とした基本方針を示すものです。
また「岩手大学研究データ管理?公開ポリシー解説」では、ポリシー本文に沿って、定義や考え方などの解説を加えています。 - 研究データの保存?管理
研究データの保存?管理は、「岩手大学研究データ管理?公開ポリシー」に基づき、関係諸法令や他の学内規定、その他研究に係る契約及び、それぞれの研究分野の特質や倫理的要件を踏まえ、研究者自身が決定することができます。
研究データの保存方法は、これまでご利用の保存方法に加え、保存先の選択肢の一つとして下記の「GakuNin RDM」の使用が可能です。- GakuNinRDM(研究データ管理サービス)
「GakuNin RDM」とは、国立情報学研究所(NII)が提供している研究データ管理サービスです。
研究者は本サービスのクローズドなファイルシステムで共同研究者とデータ共有を始めることができます。研究プロジェクト中に生成されるファイルを保存して、バージョン管理やメンバー内でのアクセスコントロール、メタデータの登録や管理ができます。また、研究公正への対応として研究証跡を記録する機能を有します。RDMとは「研究データ管理(research data management)」を意味します。 - 学術認証フェデレーション
岩手大学は国立情報学研究所(NII)が主体となって運営している学術認証フェデレーション(学認:GakuNin)に参加しているため、上記「GakuNin RDM」へアクセスする際は、学術認証フェデレーションを通じ、アクセスすることが可能です。 - GakuNin RDMユーザーマニュアル
- GakuNinRDM(研究データ管理サービス)
- 研究データの公開及び留意点
研究データの公開方法、公開範囲、公開条件等については、 研究者自身が決定 することができます。
また、公開する研究データは、FAIR 原則(注1)に基づき、公開することが望ましいですが、契約等において別段の定めがある場合は、その条件に従う必要があります。
例えば以下のような研究データについては 公開できません。- 個人情報、著作物など、法的に保護される研究データ
- 機密保持等の観点から公開に制限がある研究データ
- 契約によって制限が課された研究データ
- 安全保障輸出管理の対象になっている研究データ
- 倫理的要件等から公開に適しない研究データ
- 公開により第三者の利益を害する恐れがある研究データ 等
- FAIR 原則
研究成果である研究データの公開と共有のための原則で、Findable(検索可能)、Accessible(アクセス可能)、Interoperable(相互運用可能)、Reusable(再利用可能)を略した頭字語からなっている。(図書館情報学辞典第5版より)
問い合せ先
論文の即時オープンアクセス化、研究データ管理?公開ポリシーに関すること
研究?地域連携課
019-621-6580
kenkyou[at]iwate-u.ac.jp
リポジトリに関すること
図書館(学術情報課)
019-621-6083
eprint[at]iwate-u.ac.jp
学認フェデレーションに関すること
情報基盤センター
019-621-6096
isic[at]iwate-u.ac.jp





